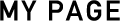
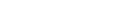
Webセミナーでは、チャット形式でいくつかのご質問にその場でお答えいたしましたが、本当にたくさんの方にご質問をいただきましたので、特に多かった質問を回答と合わせて職種別にまとめました。
ぜひご覧ください。
私が関わっている防災という仕事においては、東京都はひとたび津波や高潮等の浸水被害が生じれば甚大な被害が生じることから、このような災害から都民の生命・財産を守るため、迅速に事業を進めていかなくてはいけません。そういった意味で、日々スピーディな対応を心がけています。
コツというほどのものではありませんし、当たり前のことなのですが、筋道を立てて丁寧にお話しをするということを心がけています。また、問合せなどがあった際には、なるべく迅速な対応を心がけています。
東京都では、本当にたくさんの事業を行っていますので、それらの事業に対し、自ら学びながら積極的に関わっていくという主体性や積極性が必要ではないでしょうか。
初めのうちは、初めて携わる施設ばかりだと思いますが、自分から進んで学び仕事を進めていくという積極性を有した人でしょうか。また、学んだ知識を応用して考えられたり、関連する過去に経験した出来事を今と結びつけて考えられるような、引き出しが多く柔軟性がある人も求められている気がします。
私の働く職場では、例えば、予算等は事務職の人と調整等を行っていますし、日々の業務の半分くらいは、別の技術職や事務職の方と仕事をしています。また、どこの職場に行っても、庶務を扱う事務職の方とは日々一緒の職場で働くことになると思います。
多様なフィールドを持つ東京都で働くからには、将来的には、今の局だけでなく、他局にも異動し別の事業を経験してみたいと考えています。将来的にやはり今働いている局で働きたいと思えば、局に戻ることも希望できますので、まずはいろいろなことを経験してみたいという思いですし、新しいことを経験できるという事には、楽しみを感じています。
私の場合は、年明けから少しずつ試験勉強を進めていったという感じです。
私の職場では、耐震化推進条例の対象建築物の所有者様への働きかけや、耐震関連のイベント等で都民の方と接する機会があります。都民の方からの問い合わせの電話も多いです。
説明のタイミングを心得ている人です。なにか事業を行うとき、建築職の上司だけでなく、経理や文書(法律)関係の事務職の方々への説明や、場合によっては区市町村など外部の方々の了承や協力が必要なことが多々あります。そのタイミングを上手く計れる人はできる人だなと感じます。
とにかく聞きまくることです。知らない法律、用語など、日々の業務の中で、逐一自分で拾っていくかいかないかで大分差が出ると思っています。自分の業務だけでなく、隣の係の業務なども、聞いてみると皆さん親切に教えてくださいます。
仕事の手順を先回りできるようになった時です。はじめは一歩一歩手さぐりでやっていた仕事も、成長するとゴールから逆算して段取りが組めるようになります。
低いというよりも、あまり感じたことはありません。
建築職の仕事は多岐に亘るので、いろいろなことがやってみたい!というチャレンジ精神あふれる人だと思います。
私の課では管理職を含めた32人中、15人が女性です。他の部署と比べて、女性の比率は少し高いかもしれませんが、特別高いわけでもないと思います。
現時点では感じたことはありませんが、将来、家庭との両立について考える時が来るだろうなと思っています。技術職だから感じることは特にありません。
かねてより機械に興味があり、職業として携わりたいと考えたためです。
例えば再開発では、建物を建てるときに導入する空調の省エネ性能、エネルギー効率の評価などで機械職が活躍します。
水素社会のようにまだ誰も現実のものとして見たことのない世界も、東京都の技術職の力で創り上げていくことができると思います。
東京都のインフラを支える機械設備関係に携わることができます。人口が多い分設備も多く規模も大きいところが魅力です。
建物を建てるときに導入する空調の省エネ性能、エネルギー効率の評価などで機械職が活躍します。
公務員は、公共サービスという観点で仕事を進めるため、より都民の方の視点に近い考え方でサービスを提供でき、身近に声を聴くことができます。
都民の方と密接に関われる仕事をしたいと思ったことと、自分のやった仕事が日頃の生活の中で実感できることを重視しました。
固いイメージではなく、気軽に団欒できる雰囲気です。
東京都の職員は、区部や多摩、島など、様々なフィールドで活躍することができ、局によっても政策が様々です。局内においても、計画を立てる部署、設計をする部署、工事をする部署、維持管理する部署など多岐にわたることから、様々な仕事を行いながら、自分が成長できることがやりがいです。その反面、異動によって業務内容が大きく変わるときは大変なこともあります。
専門試験は電子工学を専攻していたため、大学時代の勉強の復習でした。教養試験は本屋に売っている予備校が出しているテキストをコツコツと地道に勉強しました。
東京都は現場を持っているということを事前に聞いておりましたが、実際に仕事をしてみると、現場で直接設備に触れて、メンテナンスの仕事をしていることに驚きました。
水道局では、水の需要量や給水エリアの変更が考えられるため、それを見据えた設備の構築が今後行われていきます。同様に、今後様々な局で、オリンピックを見据えた施設・設備の構築が行われると思います。
新規採用時にはチューター制度というものがあり、先輩職員がOJT形式で、仕事をバックアップしてくれます。異動時のOJTは部署によって異なります。実際に、私が設計業務に初めて携わったときには、先輩とOJT形式で業務を進めておりました。しかしOJTでなくてもベテランの先輩に聞けば、大抵教えてくれます。
同僚は、分からないことや相談事があれば、気軽に話しかけやすい人が多いです。また、仕事を客観的に見れる、バランス感覚の優れている先輩に憧れます。
民間でも言えることではありますが、難しい専門用語を使わず、なにも知らない人にもわかるような、簡単な言葉で説明することかなと思います。
あります。私が現在携わっている設計業務では、施設や設備を建設するに当たり、関係する自治体と協議をしながら設計を進めております。